
日本の識字率を上げた立役者!寺子屋の教育スタイルを知っておこう

皆さんは「寺子屋」という言葉を知っていますか?
かつて日本に存在した教育機関で、生活に必要なスキルや知識を子どもたちに教えていました。
そんな寺子屋ですが、実は日本国内の識字率を上げていた重要な役割を果たしていたのはご存知でしょうか?
なぜ寺子屋が識字率を上げる立役者となったのか。
その理由を寺子屋の役割や設立の背景、教育スタイルの側面から紐解いていきましょう。
寺子屋とは?歴史や教育スタイルをご紹介
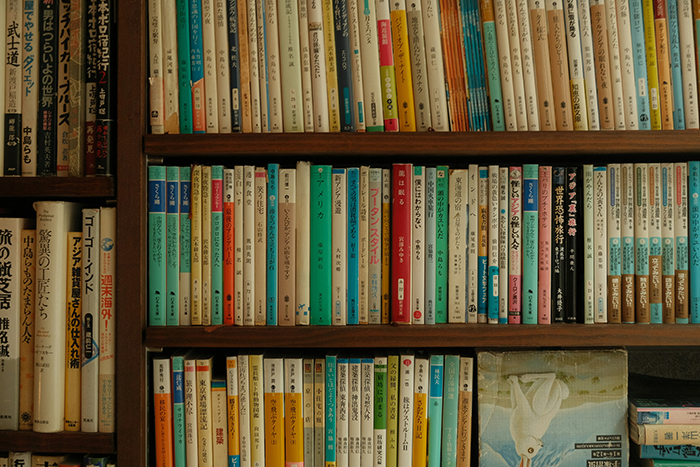
寺子屋の起源は室町時代からさかのぼります。
もとはお寺に寝泊まりしながら師匠が弟子に教育を施していたのが始まりでした。
その後江戸時代に入ってから庶民の間に広まったと言われています。
寺子屋が広まった背景
寺子屋が広まった背景のひとつに、親の多忙により子の教育を外部委託する必要性があったと言われています。
当時生きていくために必要な教育やスキルの取得は家庭間で行うべきという考えが主流でした。
学校だけでなく、今でいう託児所や学童保育の側面も寺子屋は担っていたと考えられますね。
さらに、寺子屋が広まった背景は以下の理由があると言われています。
① 読み書きと計算スキルを会得する重要性
江戸時代は泰平の世になり、戦国時代に比べると内乱で命を落とすリスクが大幅に減りました。
そのことから、人々は文字の読み書きや計算のスキルを持つことの重要性を考えるようになります。
さらに、江戸幕府からの重要な伝達は街中に建てられた「高札」(こうさつ:看板の一種)で共有されました。
つまり、文字が読めなくてはその内容を把握できず、生活に支障を起こすリスクがあったのです。
② 出版技術の伝達
出版技術が当時の大都市だった京都から政治の中心地だった江戸に伝わりました。
さらに、当時の娯楽品だった貸本文化も上記の技術により生まれました。
その結果これらの技術が識字率を上げる後押しとなったとも言われています。
③ 下級士族の雇用を作る
武士の中でも下級の身分の者は、生活苦があったと言われています。
その結果、内職として寺子屋の講師の職業は貴重な収入源となりました。
つまり、現代社会でいう「副業で稼ぐ」イメージです。
加えて社会貢献・教育普及として考えるとWIN-WINな関係性だったといえるでしょう。
④ 利息の計算
貨幣文化が江戸時代に生み出され、事業での金銭の融資や貸し借りで利息の概念が生み出されました。
その計算を行うために、そろばんを使った計算のスキルを学ぶ必要があったのです。
寺子屋に通う年齢と学費
寺子屋は義務教育として定義されていません。
そのため、一定の年齢で必ず通わなくてはいけない仕組みではありませんでした。
そこで、様々な年代の子供が1つの教室に集まっていたと言われています。
一方で、現代の日本では小中学校が義務教育と定義され、年度(毎年4月1日〜翌年3月31日)の間で満7歳を迎える子供が小学校に通い始めます。
また、原則同い年の子たちが一つの教室に集まって授業を受けるため、この2点は現代の学校教育と異なるスタイルといえるでしょう。
学費は明確な基準はなく、家庭の経済状況によって柔軟に金額を決めていました。
現金だけでなく食品や物品を納めることで学費の代わりにしていた時もあったようです。
寺子屋の教育内容を見てみよう

寺子屋の主な教育内容は「読み・書き・そろばん」です。
① 読み:文字を読む。
② 書き:文書を正しい文法で書く。
③ そろばん:当時の計算機であるそろばんを活用して計算をする。
加えて、寺子屋では学問だけでなく、身の回りの清掃や他者への礼節(親や師匠など年長者への礼儀や同年代の友達づきあい)も教えていました。
男子とは対照的に、幕末期の女子は「裁縫」「茶の湯」「生け花」など、男子と異なりより生活に根差した内容が多かったと言われています。
寺子屋独自の教育スタイル
寺子屋では現代でも使われている、最先端の教育手法がすでに使われていたと言われています。
そのため、独自の教育スタイルは明治期海外から訪れた外国人にも多く驚かれました。
① 個々に応じた独自のカリキュラム
当時は子供が親の職業を継ぐのが通例でした。
そのため、将来の職業に合わせて教材を変えて指導していました。
② 双方向型の授業システム
講師が一方的に生徒に話す授業だけではなかったと言われています。
生徒同士でわからないことを教えあうスタイルが主流でした。
③ 生活に根差した実用的な授業構成
生活に必要な知識などを中心に教えていました。
具体的には読み書きやそろばんを使った計算、将来の仕事で使うスキルが当てはまります。
寺子屋の就学率・識字率はどのくらいだった?
上述の背景から、寺子屋は都市部のみならず地方や農村部へも広まっていきました。
その背景から江戸時代の後半である嘉永年間(1848〜1855年)では70%程度の就学率があったと言われています。
また、1850年代の識字率は世界でもトップクラスの識字率でした。具体的な数値は以下の通りです。
| 対象 | 識字率 |
|---|---|
| 武士階級 | ほぼ100% |
| 庶民男性 | 約50% |
| 庶民女性 | 約20〜30% |
| 全体 | 約70% |
明治時代以降の学校教育

明治時代になると「学制」が発布され、教育システムが大きく変わります。
「小学校」「中学校」「大学」の3つの教育機関が設立され、うち小学校は義務教育となりました。
小学校の設立により寺子屋は姿を消しましたが、一部の師匠は引き続き教職の仕事に就いていたようです。
2020年代の学校教育を見てみよう
その後学制は何回か改変され、現代の義務教育は1947年に確立しました。
日本の義務教育は6歳から15歳までの9年間で、内訳は小学校6年間、中学校3年間となります。
9年間の義務教育の内容は「学習指導要領」と呼ばれる規定で決まっており、日本全国の子供が一律で同じ内容を学びます。
使用する教科書は学習指導要領に沿った内容を掲載し、国の審査を経て発行されます。
ただし、教科書は複数の企業が発行しており、市町村や学校ごとに異なることから、数学の証明問題や国語の物語など使用する文言や題材についてはわずかな違いがあるようです。
学習指導要領は数年に一度改訂されます。
そのため世代によって学んだ内容が変わっていたり、そもそも学校で取り上げられなかったという違いが生じたこともありました。
ちなみに筆者は義務教育の9年間「ゆとり教育」に当てはまっていた世代ですが、2020年代に学習塾講師をしていた際習っていない「統計」(中学数学)や高校英語で取り上げられたはずの「仮定法」が中学英語ですでに習得していることに驚きを隠せませんでした…!
ICT教育と寺子屋の教育スタイルが重なっている!?

2020年の新型コロナウイルスの流行を機に、デジタル教材を活用するICT教育が小中学校で一気に普及しました。
筆者が学習塾に勤務していた際に、ICT教育について教えてもらう機会が多々ありました。
その中で寺子屋の学習スタイルと重なる点があると感じたので、皆さんに共有します。
掲載した授業内容について
・都道府県や市町村、各学校ごとに教育内容や手法が異なります。
・本記事では、該当の個人または団体、都道府県、市町村、各学校が特定されるような内容はプライバシー保護の観点から一部詳細を伏せて記載しております。
あらかじめご了承ください。
① パーソナライズされたテスト対策
タブレットにはテスト対策や予習・復習で使える問題集が基本機能として入っています。
そして、解いていくと正答率や間違えやすいポイントについて問題集側が教えてくれます。
2回目以降は間違えやすい問題を中心に出題するため、生徒に応じてどんどんパーソナライズしていくようでした。
寺子屋でも生徒の将来や仕事に合わせた内容や教材で授業が進んで行くのが特徴です。
つまり、個別カリキュラムのシステムが江戸時代ですでに確立されていたと考えられるでしょう。
② アクティブ・ラーニングの導入
アクティブ・ラーニングは2012年頃から日本の学校教育で広まり始めた概念です。
従来では教師が児童・生徒に対して一方的に教える形が主流でした。
そこを子供たち同士が主体性を持ち、双方向に学んだ内容を発信していく手法が大きな違いです。
2020年の学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」という表現で掲載されるようになりました。
実際に筆者が子どもたちから聞いた授業内容は以下の通りです。
・1つの質問について、タブレットを介して各生徒が回答を記入して送信する。
・グループワークで出た答えをタブレットにまとめて、クラス全員に共有する。
・生徒ごとの回答はフォルダにまとめられ、他の生徒が見返せるようになっている。
・ディスカッションの資料はオンライン環境下で、全員で同時編集を行う。
寺子屋では対面型だったものの、子供達が教えあうアクティブ・ラーニングの手法がすでに取り入れられていたとのことでした。
まとめ:
寺子屋の教育スタイルは現代に通ずる!

現代の学校教育はデジタルデバイスを活用したICT教育が普及しました。
しかし、アナログの手法とてすでに寺子屋で現代と同じ教育システムを取り入れていた点は驚きます。そのため、寺子屋の授業はぜひ受けてみたいと調べれば調べるほど強く感じました。
今でも日本の教育システムは現代も独自に発展し続けています。
ぜひあなたの国の学校や教育事情の違いを、比較してもらえると嬉しいです。

















