
日本語はオノマトペが豊富!四季ごとで使えるオノマトペをまとめました
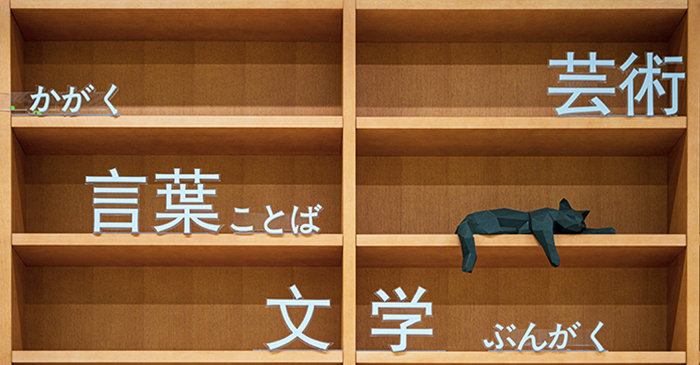
日本語は繊細な表現が多いことは有名ですが、その要因に「オノマトペ」の数が多いことも挙げられるでしょう。
オノマトペとは、自然界の音や様子、物事の状態や動きを擬音や擬態の表現で表した言葉です。
「ザアザアと雨がたくさん降ってきた。」
「ご飯をもりもりたくさん食べられて嬉しい。」
このように、筆者自身もよくオノマトペを使った表現をします。
個人的にはなくてはならない文化といっても過言ではありません。
今回は日本の四季を表現できそうな「オノマトペ」の言葉を集めてみました。
日本のオノマトペの特徴

日本語は世界で使われている言語と比べても「オノマトペ」の数が多いことが特徴です。
この理由にはいくつかの説が挙げられます。
説①:自然や四季の変化と調和した暮らしをしていた
これは日本が自然や四季と調和して生活をしてきたこと、またそのわずかな違いにも着目して風情を感じ、文学の題材にしてきたことが影響している説があります。
平安時代に書かれたエッセイ「枕草子」では、「季節は夏なのに梅の花を連想させる服装は興ざめ。」と辛口に批判するくらい季節との調和を大切にしていました。
余談ですが、枕草子では今でもあるあるな人間関係の悩みや生活のエピソードも書いてあるので、もし興味があれば読んでもらえると嬉しいです。
特に「第25段:にくきもの」に出てくる夜と蚊の話は「今でもあるある…!」と頷きながら読み進めました!
説②:動作ごとに異なる単語の数が少なかった
また、日本語では動作の詳しい意味ごとに分かれた単語は少ないため、それを補うためにオノマトペが発展した説も挙げられています。
参考に、英語の「見る」という言語の違いを共有しましょう。
- look:意識して視線を向けて見る
- see:意識せずとも自然に目に入ってきて見える
- watch:動画など、動いているものを集中して見る
このように、意味ごとの違いで動作の単語が分けられていることが、他の言語との違いといえます。
説③:音やリズムを重視した言語だから
日本語の構造や文学は、音やリズムを重視しているのが特徴です。
例えば、同じ雨の音でも大きさごとにオノマトペの違いがあります。
- しとしと
雨が「静かに」降る様子 - ざあざあ
大雨で、「音が大きく」なっている様子
この音やリズムを表す様子は児童文学や漫画・アニメ、SNSでも直感的に伝えられるため、より日本でオノマトペが発展した背景だといえるでしょう。
他の国にあるオノマトペの数を比べてみた
参考までに、他の国の言語とオノマトペの数を比べてみましょう。
- 日本語:約4,500語
- 英語:約1.500語
- フランス語:約600語
- 韓国語:約8,000語
ちなみに、世界で最もオノマトペの数が多いのは韓国語です。
その理由は意味の違いに加えて人物の性別や年代で異なるオノマトペがあるからと言われています。
例えば、動作や音を表す日本語のオノマトペに「ごろごろ」という言葉がありますが、これには複数の意味で使い分けができます。
下の例文をご覧ください。
- 雷の音
雷なのか、空からごろごろと音が聞こえる。 - だらけて横になっている様子
昨日は暇だったので、家でごろごろしていた。 - 身体 (目やお腹)の異変
目がごろごろして痛い。ゴミが入ったかも?
日本語だと2,3の人物の年齢・性別に関わらず共通のオノマトペを使えるため、韓国語と比べるとオノマトペの数が限られると推測できるでしょう。
四季ごとのオノマトペをご紹介
ここからは、四季の様子を伝えるオノマトペを例文と一緒にご紹介します。
春のオノマトペ

① ぽかぽか
日差しが降り注ぎ、気温が温かくてのどかな様子を表します。
このような日にお花見をすると最高です。
例文)
今日はぽかぽかしている陽気で、とても気持ちが良いね。
② ひらひら
蝶や花びらが風に乗って軽やかに舞う様子を表現しています。
類似の表現で「ひらりひらり」というオノマトペもあり、ポルノグラフィティの「アゲハ蝶」の歌い出しでも採用されています。
例文)
ひらひらと桜の花びらが手のひらに舞い降りてきた。
③ ニョキニョキ
草木やたけのこが地面から芽を出し、天に向かって伸びていく情景をイメージします。
スタジオジブリの「となりのトトロ」でも、植物の種が芽吹くシーンが出てきていましたね。
まさにニョキニョキと植物が芽吹く様子を力強く表現しています。
たけのこが伸びる様子を表現した手遊びである「たけのこニョッキ」でも、このオノマトペが採用されています。
小学生の時に部活動のメンバーでやりましたが、非常に盛り上がりました。
夏のオノマトペ

① じめじめ
湿気がある天候の様子を表現します。
とりわけ梅雨の期間中に使われやすいオノマトペです。
例文)
今日はじめじめしている陽気だから、食事の保存には気をつけよう。
② ギラギラ
光が眩しいだけでなく、刺さるような強さを持つ様子を表します。
とりわけ2025年の日本の夏はまさにうってつけなオノマトペでしょう。
似ているオノマトペに「きらきら」がありますが、「ぎらぎら」と比べると輝いて綺麗であり、見ていて楽しい気持ちになる違いが挙げられます。
例文)
太陽がギラギラ照りつけていて、少し歩くだけでも日焼けしそうだ。
③ シャリシャリ
かき氷やアイスキャンディーなどの食感を表現したオノマトペです。
最近は口当たりの優しいかき氷が増えましたが、氷の粒を感じる昔ながらのかき氷はまさにこの「シャリシャリ」という食感を楽しむことができます。
例文)
このアイスキャンディーはシャリシャリとした食感でとてもおいしい。
秋のオノマトペ

① かさかさ
地面の落ち葉を踏んだ時の音を表します。
同じ意味を持つ「がさがさ」というオノマトペもありますが、こちらはより重たい印象を聞く人に与えます。
例文)
かさかさと音を立てながら並木道を歩いていく。
② ぴいぷう
11月頃の北風が吹く様子を表現したオノマトペです。
日本の童謡である「たきび」にも、このオノマトペが出てきています。
例文)
北風がぴいぷうと吹いてきたから、もうじき冬が近いだろう。
③ さらさら
稲穂や草が風に吹かれて擦れる音を表現しています。
黄金色の田んぼに稲穂が揺れる様子は毎年秋に見られる美しい景色です。
例文)
稲穂がさらさらと音を立てて揺れていた。
冬のオノマトペ

① しんしん
雪が静かに降り積もっていく様子を表します。
筆者は昔日本の中でもとりわけ雪が多く降る地域に住んでいましたが、まさに音が世界から無くなったかのような静かな雰囲気を感じることができました。
例文)
雪がしんしんと積もっていく。
② ひんやり
気温が低く、肌触りが冷たい様子を伝えるオノマトペです。
アイスクリームやかき氷など、食事の冷たさを表現したい時にも使います。
例文)
朝家を出たらひんやりとした空気を肌に感じた。
③ ぶるぶる
寒さが強く、震える様子を表します。
似ているオノマトペには「ぷるぷる」という言葉がありますが、こちらはゼリーやプリン、スライムなど弾力のある物体が揺れる時の動きを表現しているのが特徴です。
例文)
外で待っていたが、あまりの寒さにぶるぶる震えてしまった。
まとめ:
オノマトペで表現できる四季がある
自然・四季の音や様子を表現しているオノマトペは、日本の伝統的な暮らしと深く結びついています。
私たちは普段目で見て四季や自然を感じていますが、その状態でさらにオノマトペの音や意味を感じると、より五感を働かせてじっくりと味わうことができるのではないでしょうか。
ぜひこの記事で紹介したオノマトペと一緒に、日本の四季を味わってもらえると嬉しいです。
( %e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e )

















